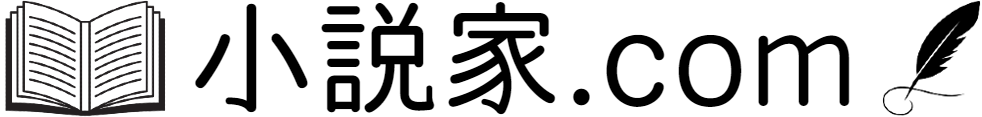都会の雑踏から少し離れた山間に、その駅はひっそりと佇んでいた。駅名も、正確な場所も、いつからその駅が存在しているのかも誰も知らなかった。ただ、少し物好きな人々の間で「幽霊駅」として語り継がれているだけだ。
大学生の笠井凛太郎は、旅先で出会った老人からその駅の話を聞き、興味本位で向かうことにした。祖父から聞かされて育った「戦時中の秘密基地」とか「異世界に繋がる扉」といった話に心をときめかせながら、少し古びた列車に乗り込んだ。
車内にはほとんど人影がなかった。窓から見える景色も次第に都会のビル群から山並みや木々に変わっていき、やがて列車はトンネルに差し掛かった。そこを抜けた時、辺りは霧に包まれていた。笠井が見つめる先には、駅のプラットフォームが静かに広がっている。小さな木造の駅舎がひっそりと佇み、時が止まったような雰囲気が漂っていた。
笠井は好奇心に駆られるまま駅舎へと足を踏み入れた。中には古びたベンチが並び、窓口の隅には埃まみれの時刻表が置かれている。だが、その時刻表にはどこか違和感があった。現在のものではなく、年代物の紙に手書きの数字が書かれている。どうやらここは、何十年も前に時が止まっているらしい。
「どうしてこんな場所が存在しているんだろう?」と考え込む笠井。その時、背後から人の気配を感じた。振り向くと、見知らぬ青年が立っていた。彼はどこか浮世離れした雰囲気を持ち、白いシャツと黒いパンツを着ている。
「君も、ここに来たのか?」青年が問いかけた。
「ええ、噂を聞いて…。でも、まさかこんな場所が本当にあるなんて思ってもみませんでした。」
「この駅は、忘れ去られた人々が集まる場所だよ。」青年は静かに言った。
「忘れ去られた人々?」
「そう。生きることに疲れて、誰にも気づかれずに消えてしまった人たちさ。」青年の言葉はどこか切なく響いた。
笠井は何か胸の奥がざわつくのを感じた。彼は何も言えずに立ち尽くし、ただ青年を見つめた。すると、青年は笠井に手を差し伸べ、「君も一緒に来ないか?」と誘った。その瞬間、笠井の胸に強い疑念がよぎった。まるでここに留まってはいけないと言われているような感覚がしたのだ。
「僕は…戻りたいんです。」そう答えると、青年は静かにうなずき、少し悲しそうな笑みを浮かべた。
「そうか、なら君はもう帰るんだね。でも、気をつけて。忘れ去られた人々は、君をいつでも待っているよ。」
青年の言葉が響く中、笠井は駅を後にした。戻った列車は元の山道を走り出し、笠井が再びトンネルを抜けると、駅は霧の中に消えてしまった。