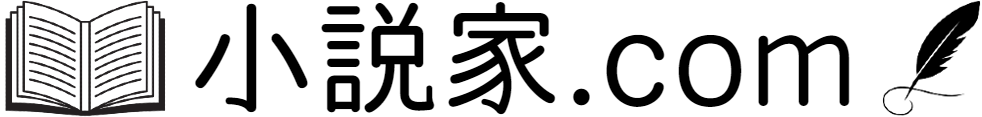最初に気づいたのは、写真の中の人の表情が変わっていたことだった。
私の部屋には、祖母の遺影が飾ってある。去年の夏に他界した祖母は、写真の中でいつも穏やかな笑顔を浮かべていた。しかし、ある朝、その表情が違っていた。口角が僅かに下がり、目が鋭くなっていたのだ。
「気のせいよ」
そう自分に言い聞かせた。写真が勝手に変わるはずがない。きっと光の加減か、私の疲れた目がそう見せているのだろう。
だが、それは始まりに過ぎなかった。
数日後、私は古いアルバムを見ていた。そこには、小学生の頃の写真がたくさん収められている。運動会で走る私、家族旅行で海に入る私、誕生日ケーキの前で笑う私。
「あれ?」
ページをめくると、見覚えのない写真があった。確かに私なのだが、記憶にない場面だった。校庭で一人、ブランコに座っている。周りには誰もいない。夕暮れ時らしく、私の背後に長い影が伸びている。
不思議に思いながらもその時は気にしなかった。けれど、次の日、同じアルバムを開いた時、その写真はさらに不気味なものに変わっていた。
ブランコに座る私の後ろに、見知らぬ人影が写っていたのだ。
背が高く、黒い服を着た大人の人影。顔は写っていない。いや、正確には、そこだけがぼやけていて見えないのだ。
震える手でアルバムを閉じた。冷や汗が背中を伝う。こんなことがあるはずがない。写真は過去の記録だ。変わるはずがない。
その夜から、私は他の写真も確認し始めた。スマートフォンに保存された写真、パソコンの中のデータ、実家から持ってきた古い写真たち。
すると、恐ろしいことに気がついた。
写真の中の「イ象」が、少しずつ変化していたのだ。
人々の表情が歪み始め、背景に不自然な影が増え、時には見知らぬ人物が写り込むようになった。特に、私が写っている写真は顕著だった。
友人との集合写真では、私の隣に必ず黒い服の人影が立っている。一人で撮った自撮りでは、背後の鏡に見知らぬ顔が映り込んでいる。
そして最も恐ろしかったのは、写真の中の私の表情が、日に日に恐怖に歪んでいくことだった。
「これは現実じゃない」
私は必死に自分に言い聞かせた。けれど、現実は私の否定を無視して、さらに恐ろしい方向へと進んでいった。
ある朝、会社の同僚が不思議そうな顔で私に声をかけてきた。
「ねぇ、昨日のみんなで撮った写真、見た?」
私は既に見ていた。そして、そこに写っているものを誰にも見せたくなかった。写真の中の私は、完全に違う人のような表情をしていた。目は虚ろで、口は不自然に歪み、肌は死人のように青白い。
そして、私の背後には、いつもの黒い人影が。
「ごめん、私、写真見るの苦手なの」
それから、私は必死に写真を避けるようになった。自撮りもせず、集合写真も断り、SNSもすべて削除した。
けれど、逃げることはできなかった。
信号待ちでスマートフォンを見ていた見知らぬ人が、突然悲鳴を上げた。画面に写り込んでいた私の姿が、あまりにも異様だったのだ。
電車の窓に映る私の姿も、防犯カメラに映る私の姿も、すべてが少しずつ歪んでいった。
ついには、鏡に映る自分の姿さえも。
今、私は部屋の隅で震えている。スマートフォンのインカメラを開くと、画面に映るのは、もはや人間とは思えない姿だ。
黒く窪んだ目、灰色の肌、不自然に曲がった首。そして、私の背後に立つ黒い人影は、今では完全に実体を持っている。
カメラを消しても、その存在は消えない。むしろ、より鮮明に感じる。冷たい吐息が首筋に当たり、長い指が肩に触れる。
写真は嘘をつかない。写真は真実を写す。
そう、これが私の本当の姿なのかもしれない。世界が私に見せたかった真実の「イ象」。
スマートフォンの画面が突然点灯する。カメラが勝手に起動し、私を写し始めた。
写真の中の私は、もう笑っている。
後ろの黒い人影と同じように。