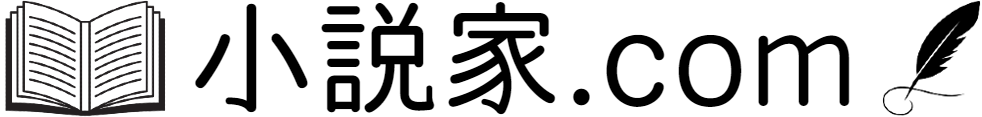桜の花びらが舞い散る4月の午後、私は古い写真館の前で足を止めた。看板には「思い出写真館」という文字が、少し色褪せながらも確かに刻まれている。祖母が亡くなって、もう半年が経つ。遺品整理の際に見つけた一枚の写真の裏に、この写真館の住所が記されていた。
「いらっしゃいませ」
ドアを開けると、小さな鈴の音と共に、白髪の老人が穏やかな笑顔で迎えてくれた。店内は、時が止まったかのような静けさに包まれていた。古びた木製のカウンターの向こうには、無数の写真が壁一面に飾られている。
「あの、これについてお伺いしたいのですが」
私は鞄から取り出した写真を差し出した。それは50年以上前のものだ。若かりし日の祖母が、満開の桜の下で微笑んでいる。その横には見知らぬ青年が立っている。
「ああ」老人は写真を手に取り、懐かしそうに目を細めた。「これは確かに、私が撮影した写真ですね」
「実は、この男性のことについて知りたいのです」私は声を潜めるように言った。「祖母の遺品から見つけたのですが、家族で知っている人が誰もいなくて」
老人は静かにため息をつき、奥の部屋へと私を招き入れた。そこには古い記録簿が、整然と並べられていた。
「お客様のお祖母様は、毎年この時期にいらっしゃっていました」老人は一冊の記録簿を開きながら語り始めた。「そして、その青年も」
記録簿には、祖母の名前と共に、「田中陽一」という男性の名前が記されていた。日付は、毎年4月3日。私の目を疑うように、その記録は20年以上も続いていた。
「お二人は、この写真館で出会いました」老人は懐かしそうに語り続けた。「陽一さんは、当時売れない小説家志望の青年でした。お祖母様は、この界隈で評判の和菓子屋のお嬢さんで」
「でも、なぜ家族は誰も知らないのでしょう?」
「それはね」老人は少し言葉を選ぶように間を置いた。「二人の関係は、ある意味で完璧すぎたのかもしれません」
その日の夕方まで、老人は二人の物語を語ってくれた。陽一は、祖母の作る和菓子に心を奪われ、毎日のように店を訪れていた。祖母もまた、彼の夢を応援し、彼の書く物語に耳を傾けていた。しかし、祖母には既に縁談が決まっていた。
「最後に二人が会ったのは、この写真を撮った日です」老人は静かに言った。「その後、陽一さんは東京へ向かい、作家として成功されました。でも、お二人は約束したんです。毎年この日に、それぞれがここを訪れることを」
私は息を呑んだ。祖母が毎年4月3日に、「ちょっとお出かけ」と言って出掛けていたことを思い出していた。
「では、田中陽一さんは…」
「はい、彼もずっと来られていました。ただ、お二人は決して同じ時間には来ません。朝は陽一さん、夕方はお祖母様。それが、お二人の決まりでした」
老人は立ち上がり、古いアルバムを取り出した。そこには、20年以上に渡る二人の写真が、丁寧に収められていた。同じ場所で、同じポーズで、ただし決して一緒ではない写真の数々。
「本当の愛とは、必ずしも結ばれることではないのかもしれません」老人は静かに言った。「時には、このように互いを思いながら、別々の人生を生きることもまた、愛の形なのでしょう」
私は黙ってアルバムを眺めていた。最後のページには、祖母が亡くなる直前に撮影された写真があった。老いてなお凛として美しい祖母の姿。そして、その隣のページには、同じ日に撮影された初老の男性の写真。二人は、五十年の時を超えて、同じ優しい眼差しを向けていた。
写真館を後にする時、春の夕暮れが街を優しく染めていた。私は、祖母が毎年見ていた同じ景色を見上げた。桜の花びらは、相変わらず静かに舞い落ちている。
その日以来、私は毎年4月3日に、この写真館を訪れることにしている。そして、二人の写真の前で、言葉にならない物語に耳を傾けるのだ。永遠に交わることのない、けれども確かに存在した、祖母の春の記憶に。